海や川がよごれると…
もし海や川がよごれると、わたしたちのくらしや環境(かんきょう)にどのように影響(えいきょう)するのでしょう。
揖保川は、あゆなどの魚がすめないほどよごれた川でした。下水道が整備(せいび)されたことによって、だんだんと水質(すいしつ)がよくなってきました。今では、とてもきれいな川にもどっています。
海や川の水がよごれる原因
- 工場などからの排水(はいすい)
- 家庭からの排水(はいすい)
- ごみのポイ捨て
海や川がよごれると
- 川の水がきたなくなって生き物がすめなくなります。
- 川の水がにおったりします。
- カやハエなどが発生(はっせい)します。
- 水道の水がにおったり、飲めなくなったりします。
- 赤潮(あかしお)が発生して、海の魚が死にます。
- 魚が食べられなくなります。
きれいな川や海を守るために、わたしたちにできることは何でしょう。
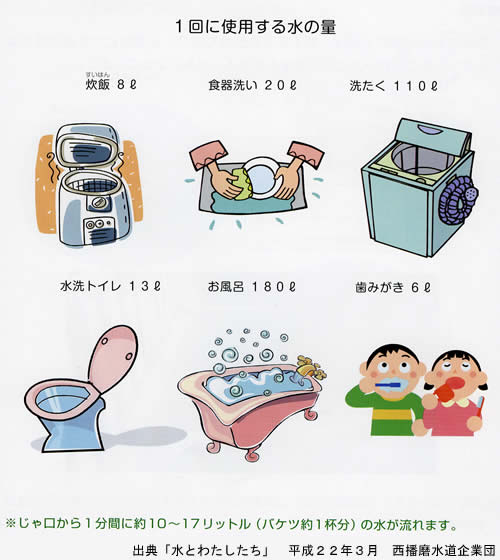
質問.1 じゃぐちをひねるといつでも水が出るのはなぜですか?
回答.1
わたしたちの家や工場、学校で使う量に合わせて、水源地(すいげんち)から排水池(はいすいいけ)に送る量を24時間監視(じかんかんし)しているからです。
質問.2 水道の水には何も入っていないのですか?
回答.2
水道の水には消毒(しょうどく)のために次亜塩素酸(じあえんそさん)ナトリウム溶液(ようえき)が入っています。また、地下水を使っているので、自然のミネラル分(カルシウム、マグネシウム、ナトリウム)などがふくまれています。
質問.3 日本で一番最初にできた水道は?
回答.3
日本で一番最初にできた水道は、石や木を使った溝形(みぞがた)で1590年頃(今から約420年前)徳川家康(つくがわいえやす)が、現在の東京都三鷹市(とうきょうとみたかし)にある井の頭池(いのがしらいけ)から、江戸(現在の東京都の中心部)までひいたといわれています。
質問.4 たつの市の水道はいつから?
回答.4
1953年(今から56年前)に送水(そうすい)を始めました。その後、どんどん広がりました。今、年間の送水量(そうすいりょう)は約850万立方メートル、1日の平均送水量(へいきんそうすいりょう)は約22,000立方メートル(学校のプールにたとえると約75杯分)になります。
質問.5 市場水源地(いちばすいげんち)が停電(ていでん)になれば、水を送れなくなり断水(だんすい)してしまうのですか?
回答.5
市場水源地(いちばすいげんち)には、送水(そうすい)パイプを動かすことのできるディーゼル発電機(はつでんき)が1台あります。停電(ていでん)になると自動的(じどうてき)に発電機(はつでんき)のエンジンがかかり、発電を始めるため、断水(だんすい)になることはありません。また、短時間の停電(ていでん)ならば、排水池(はいすいいけ)にたくさん水をためているので、すぐに断水(だんすい)することはないのです。


更新日:2025年08月13日